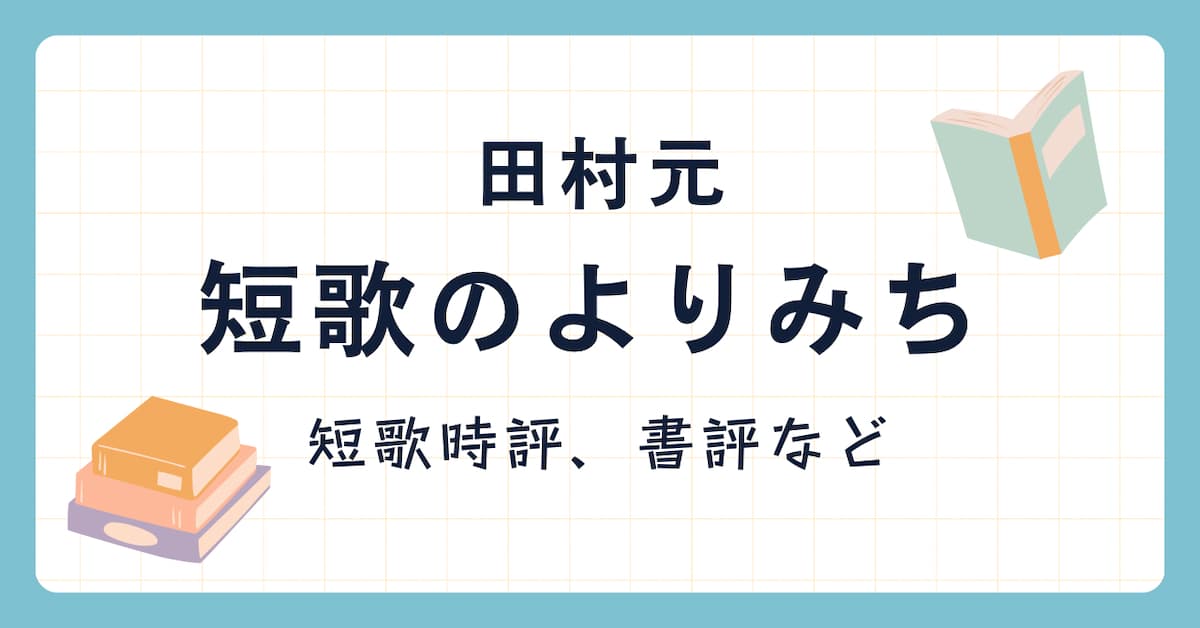「現代短歌」で連載中の寺井龍哉「歌論夜話」が実に面白い。寛保二年(一七四二年)に、田安宗武に歌論の提出を命ぜられた荷田(かだの)在満(ありまろ)が三日で書き上げたと言われる「国歌八論」を読み進めながら、短歌に関わるもろもろを縦横に論じていて読み応えがある。
連載三回目となる十一月号の「言葉が歌になるとき」は、私の最近の関心に重なるところも多く、特に面白かった。
それ歌はことばを長うして心をやる物なり。
「国歌八論」の中の右の一文をたよりに、言葉が「歌」になる条件とは何かを考察している。この一文の中の「ことばを長うす」という表現は、『書経』の「歌(うた)は永言(えいげん)し」を踏まえたものだという。寺井は『書経』のこの一節のあとに登場する二つの歌に、どちらも押韻が用いられていることに着目し、次のように述べている。
すくなくとも、『書経』の段階では、類似の音や句の反復によって発生するリズムのようなものこそ、「歌」たることのひとつの条件だったのだろう。
「類似の音や句の反復」つまり、押韻やリフレインに、言葉が「歌」になる一つの条件を見出している。
「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ 俵万智『サラダ記念日』
さようならいつかおしっこした花壇さようなら息継ぎをしないクロール 山崎聡子『手のひらの花火』
寺井は、右の歌などを「頭韻的な反復」の例として引き、「そしてこれらはいずれも、それぞれの歌人の代表歌の格が与えられているように思えてならない」と言う。
ここまでが寺井の論の要約である。私が共感したのは、リフレインの歌が「歌人の代表歌」の格を与えられているという点だ。
先日、たまたま短歌のリフレインについて話す機会があり、例歌として次のような歌を引いた。
ひまはりのアンダルシアはとほけれどとほけれどアンダルシアのひまはり 永井陽子『モーツァルトの電話帳』
子がわれかわれが子なのかわからぬまで子を抱き湯に入り子を抱き眠る 河野裕子『桜森』
寺井の引く「頭韻的」なリフレインとはやや異なるが、これらもリフレインの使用によって、それぞれの歌人の代表歌となった例と考えていいだろう。なぜリフレインが代表歌、名歌を生み出すかと言えば、言葉の繰り返しによる覚えやすさ、暗誦のしやすさといったことが大きいのではないか。
歌謡曲もそうである。私がカラオケでときどき歌うアリスの「君の瞳は10000ボルト」は、後半の歌詞がほとんどリフレインになっており、非常に歌いやすく覚えやすい。
短歌も「歌」であり「音楽」なのだということを、最近よく考える。同時に、今までの自分が、短歌を作ったり読んだりする上で、言葉の「意味」つまり「文学」に偏り過ぎていたのではないかとの反省もしている。
近年、「分からない歌」がよく議論にのぼるが、これは言葉の「意味」についての議論である。「分からない歌」を、押韻やリフレインなど、「音楽」的な観点で読み直してみたら、また違ったものが見えてくるかもしれない。もう少し考えてみたい問題である。
(初出:「りとむ」2018.1)