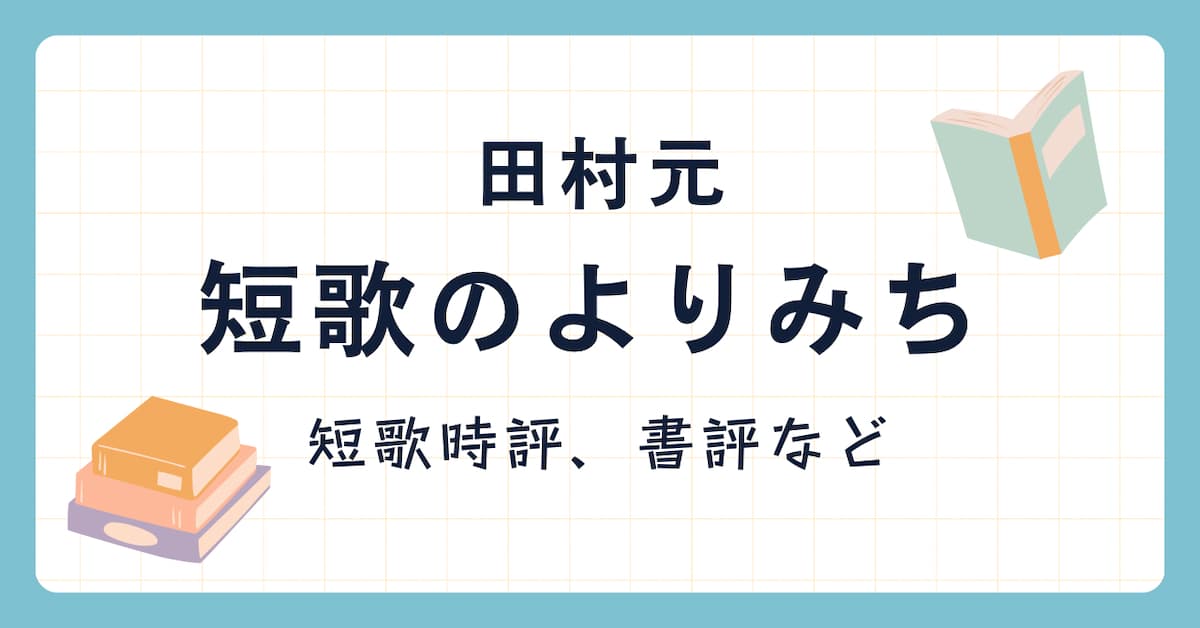松村正直の評論集『樺太を訪れた歌人たち』(ながらみ書房)が、実に面白かった。
「短歌往来」に二年間連載された「樺太を訪れた歌人たち」(北見志保子、松村英一、北原白秋などを取り上げた評論)が本書の中心となっており、それに樺太在住の歌人についての評論と、実際にサハリン(樺太)を訪れての紀行文を加え、一冊にまとめられている。
全ての文章が、樺太という土地にスポットが当てられており、短歌の評論集としては、おそらく史上初の切り口ではないだろうか。
幌内川の洲幅ゆたかに住む慣(なら)ひギリヤーク族の子ら話すアイウエオ 北見志保子
コーライト焚きつつこもるこの部屋の二重なる窓ぴたりとしまる 橋本德壽
小沼(こぬま)に来て養狐場(やうこぢやう)に養はれゐる銀黒狐(ぎんくろぎつね)いくつも見たり 斎藤茂吉
取り上げられているのはこんな歌である。先住民の「ギリヤーク族」、石炭を原料とした燃料の「コーライト」、当時の樺太で盛んだった「養狐場」など、現代の短歌ではほとんど目にすることのない言葉に想像力を掻き立てられる。こうした言葉に私はとても新鮮さを感じるが、それは裏を返せば、今までの私が樺太という土地にほとんど関心を持っていなかったということでもある。
著者は「あとがき」の中で次のように述べている。
戦後、人々の記憶から忘れ去られるままになっている樺太。現在でもなお、日本で発行される地図において樺太(南サハリン)は日本の領土でもロシアの領土でもない空白地帯とされている。これは日本政府の「最終的な帰属は未定」という公式見解に則ったものだ。そして、地図が空白なだけではなく、私たちの記憶や知識の中でも空白のままになっている。
恥ずかしながら、日本の地図で樺太が空白地帯とされているという事実を私は初めて知った。(日本政府の公式見解は外務省ウェブサイトの「北方領土問題に関するQ&A(関連質問)」というページに書かれているので、興味のある方はご覧いただきたい。)それくらい樺太は私にとって未知の世界だったし、大多数の方にとっても、同じようなものなのではないだろうか。
本書は、人々にとって「空白のまま」となっている樺太の歴史を、歌人たちの作品や足跡をたどることを通じて、現代に蘇らせることに成功している。その成功は、松村の丹念な調査と筆力によるものであることは勿論だが、短歌という詩型の特性も一役買っていると言えるのではないだろうか。
短歌は記録性に富んだ詩型であり、人々の思いや各地の風物を記録にとどめるのは得意技である。そして、歌人が文筆以外に本業を持っていることもプラスに働いている。造船技師だった橋本德壽、帝国水難救済会の理事だった石槫千亦は、それぞれ業務の一環で樺太を訪れ、作品を残している。彼らの作品には、歌人としてだけでなく、職業人としての目で見た樺太が描かれており、それを辿ることが、本書の記述に厚みをもたらしていると言える。
試みに、『樺太を訪れた作家たち』や『樺太を訪れた俳人たち』という書籍を想像してみる。どちらも、本書ほどはうまくいかないのではないだろうか。
短歌という詩型の特性と、「空白のまま」となっている樺太との邂逅によって、私たちが気づかなかった新たな歴史が描き出されている。読み物としても非常に面白い一冊だ。
(初出:「りとむ」2017.3)