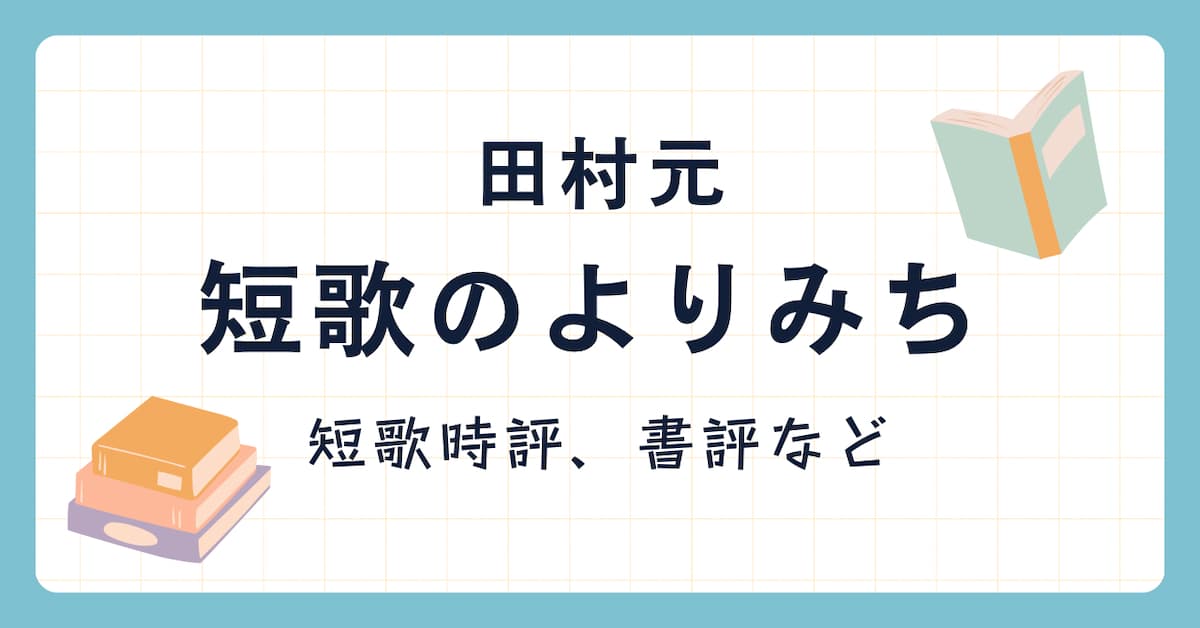山下翔の「温泉」五十首は、注目の連作である。「九大短歌」の第四号(平成二十八年十月刊)に掲載。夏に長崎の地元に帰省し、雲仙の温泉に入り、友の家に泊めてもらう。だいたいこんなストーリーだ。
ただいまときみが言ふ家の暗がりをこんにちはと明るく言ひて通りぬ
友の家に上がり込む場面である。来訪者による「こんにちは」は、その家の一員の「ただいま」よりも、半音程度明るく聞こえる。そんな発見が下の句に現れているが、それを「家の暗がり」と対置させているところがレトリカルだ。そして、この一首は、連作を読み進めるにしたがって、あるテーマへと繋がっていく。
きみもこの家に育ちたるひとりかと思へばつらいごちやごちやの玄関
友である〈きみ〉の家の「ごちやごちやの玄関」を見て、ある痛みを感じている。どんな痛みなのかは、次の歌を読めば分かる。
会はないでゐるうちに次は太りたる母かも知れず 声をおもへり
この夏をいかに過ごしてゐるならむ花火のひとつでも見てればいいが
缶ビール缶チューハイの缶たまり母の玄関せまくしてゐむ
この連作の主人公は、帰省をしているはずなのに、どんな事情かは分からないが、母親と会っていないようだ。そして母に心を寄せつつ、酒類の空き缶がたまっている母の玄関を思う。先に引いた「ごちやごちやの玄関」の歌は、連作の中での伏線になっている。
ほむら立つ山に出湯のあることのあたりまへにはあらず家族は
「家族」あるいは「家」が、この連作のテーマだ。そしてそのテーマを詠むに当たり、泊まった友の家を描くことで、自らの「家」が、間接的に描かれるような構成になっている。よく練られた連作だと思う。
テーマには直接関係ない歌にも、読ませるものが多い。
湯に浸かる時間はわづか出て休みまた入りあとは出たまま休む
爆竹のババンババンバンバンと鳴るゆふべ澄みたる山の空気に
一首目の下の句は、言葉遊びだが、手旗の「赤上げて、白下げて……」のような楽しさがある。二首目は、ドリフターズの「いい湯だな」の歌詞を踏まえたものだが、修辞の面白さと韻律とともに、この連作に昭和的な郷愁を漂わせる役割を果たしている。
「歌壇」平成二十八年二月号の歌壇賞の候補作品に、次のような山下の作品があった。
広場まで出でてまはせば二連なる精霊船はをとこのちから
挨拶に行けば引き戸を開けたるはボクサーブリーフ一丁の男
現代を生きる青年(山下は平成二年生まれ)にしては、歌の素材に妙な渋さがある。山下の作品には、ローカルで土俗的な香りが漂い、東京を中心とした都市の時間とは、異なる時間が流れているようなところがある。
私事で恐縮だが、群馬の山村で育ち、十九歳で札幌の大学に進学した時、十年か二十年くらい未来にタイムスリップしたような気がしたものだ。今ではすっかり都市の時間に馴染んでしまったが、山下の連作を読んであの時の感覚を久しぶりに思い出した。
短歌にとって、時代とは何なのだろうか。そして、新しさとは何なのだろうか。
(初出:「りとむ」2017.1)