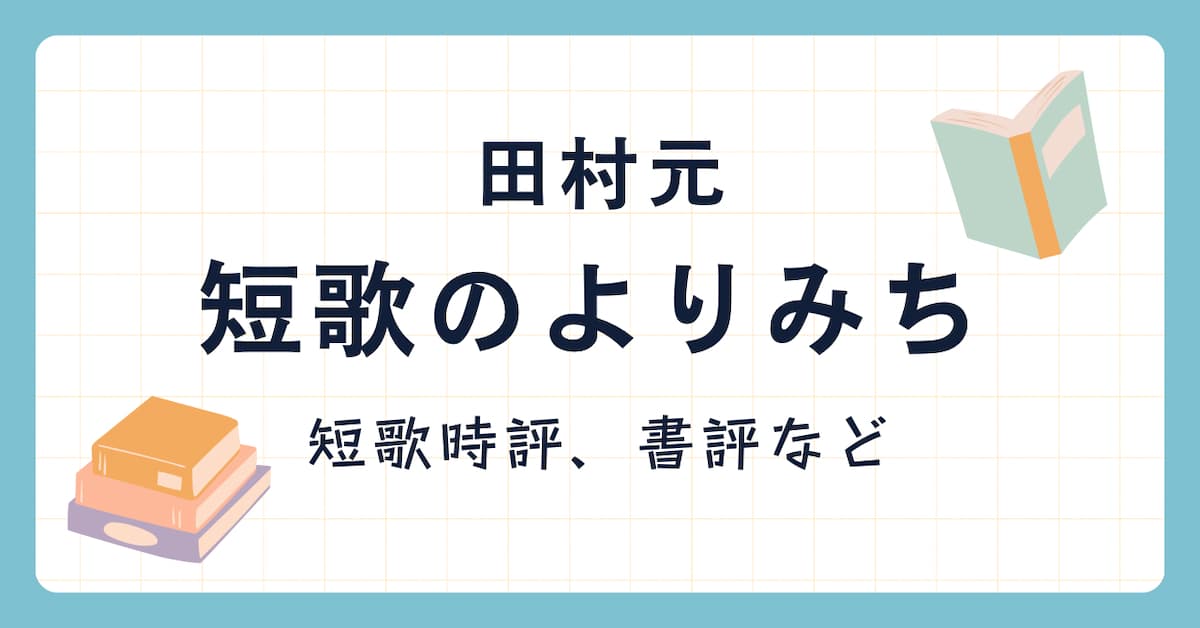二〇一六年九月八日付の日経新聞によると、十五歳から三十九歳の「引きこもり」の人は、全国で推計五十四万一千人いるとの調査結果が内閣府から発表された。引きこもりの定義は、「趣味の用事の時だけ外出する」、「近所のコンビニなどには出かける」、「自室からほとんど出ない」などの状態が六カ月以上続く人ということである。二〇一〇年に行われた初の調査からは約十五万人減ったそうだが、五十四万人の「個」のありようを想像するだけでも、なんだかくらくらとしてくる。
虫武一俊の第一歌集『羽虫群』(書肆侃侃房)は、引きこもりを経験し、それを克服していく青年の物語である。
生きかたが洟かむように恥ずかしく花の影にも背を向けている
窓枠のかたちの届く距離が日々変化して人生はおもしろい
三十歳職歴なしと告げたとき面接官のはるかな吐息
内閣府の「引きこもり」の定義に当てはまるかどうかは分からないが、三十歳まで職を持たずに過ごし、窓から差し込む日差しの距離を観察して過ごす日々を青年は送っていた。これらの歌に描かれているのは、自分に自信が持てず、社会との関わりを摑みあぐねて苦しむ孤独な青年の姿だ。
この歌集を読んで思い出したのは、岸見一郎・古賀史健『嫌われる勇気』(ダイヤモンド社)である。哲人と青年との対話篇の形式で、アドラー心理学を分かりやすく解説した一冊だが、この本に登場する青年は、『羽虫群』の青年と、どことなく似ているのだ。
『嫌われる勇気』のほうの青年は、一応仕事はしているものの、強い劣等感にさいなまれ、いつも自己嫌悪に陥っている。対人関係に悩み、新しい一歩を踏み出せないままの青年を、哲人がアドラー心理学に基いて導いていくというのがこの本のストーリーである。
一方の『羽虫群』のほうはどうだろう。
ジャム売りや飴売りが来てひきこもる家にもそれなりの春っぽさ
引きこもりの日々の中にも、この歌のように、ささやかな変化から春の訪れを感じ取る瞬間がやってくる。下の句には若干の閉塞感も込められてはいるが、外の世界へと繋がっていく兆しが一首からは感じられる。
もうおれはこのひざを手に入れたから猫よあそこの日だまりはやる
歌集の後半には、こんな風に、恋人の膝枕を詠ったと思われる歌が登場したりする。石川美南は解説の中で、「Ⅰ章から順番に読んでいくと、ひとりの青年がためらいながら言葉を紡ぎ、その過程で他者を獲得していく様子が、ほのかに立ち上がってくる」ことを指摘しているが、私も同感だ。
ここで注目したいのは、『嫌われる勇気』の青年が、アドラー心理学によって導かれたのと同じように、『羽虫群』の青年は、「言葉」(短歌)によって他者との繋がりを得ることができたという点だ。短歌は文学のジャンルの一つだが、このように時として心理学や哲学に似た役割を果たすことがある。言葉とはそもそも、その先に他者との交流を前提としたものなのかもしれないが、短歌という詩型が秘めている、どこか文学をはみ出した機能について、じっくり考えてみたくなる。
(初出:「りとむ」2016.11)