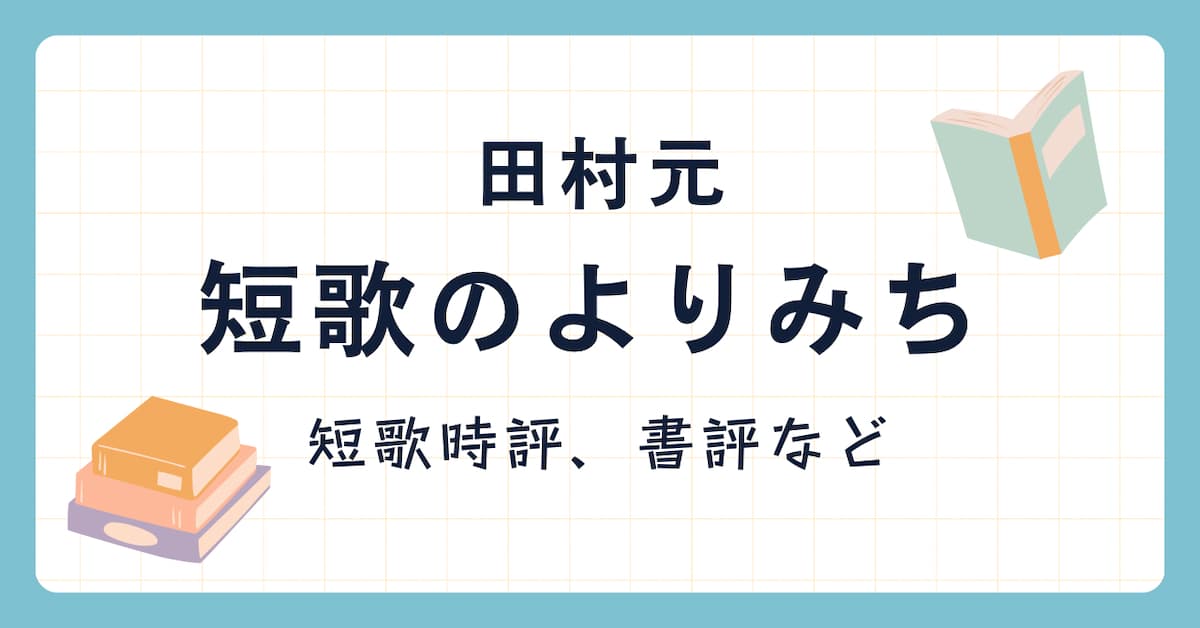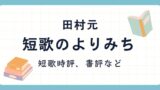蛇行せよ詩よ詩のための一行よ天国はまだ持ち出し自由 千葉 聡
歌集『微熱体』より。僕がこの作品に初めて出会ったのは一九九八年の夏、まだ短歌を作り始めて間もない頃のことだった。僕は表向きには札幌の大学の法学部生ということになっていたものの、六法全書を持って大学に行ったことはほとんどなかった。鞄の中にはいつも小説の文庫本やら、哲学書やら、岩波新書やらが詰まっていて、恋に悩めば、プラトンの対話篇から読み始めて愛とは何かを哲学史に沿って考え始めようとするような、今思えばずいぶんと悠長な日々を送っていた。(ちなみに、愛についての考察はアリストテレスまでで挫折した。)
そんなある日の午後、キャンパスの図書館の雑誌コーナーで立ち読みをしていたとき、短歌研究新人賞の受賞作「フライング」の中に右の一首をみつけたのだ。僕はただただ鼻の穴を大きく膨らませながら、何度も何度も一首を読み返していたように思う。
掲出歌は、連作中に登場する俳優の卵ケント(志半ばで交通事故死)への挽歌でもあるが、同時に短歌という詩型への賛歌という性格も持っている。例えば佐佐木幸綱の有名な作品に、
直立せよ一行の詩 陽炎に揺れつつまさに大地さわげる
という一首があるが、どちらの作品も「詩」、つまり言霊に向けて命令形で呼びかけるアジテーションの魅力はなかなかのものだ。
そして、千葉の作品には一つの問いがある。親しい友の死に遭遇するというような悲しみの淵で、僕たちにはいったい何ができるのだろうかという問いである。そんなときは「蛇行せよ」と、詩に向かって呼びかける以外にないのだ、ということを千葉の作品は教えている。
これをゲーテ風に言えば、
あんたが詩人と名のる以上は、
詩にむかって号令をかけたまえ。
手塚富雄訳『ファウスト』
ということになる。短歌が詩である限り、僕たちが歌詠みである限り、僕たちはいかなるときも言霊に向かって号令をかけ続けなければならない。短歌という詩型に携わる者にとって、詠い続けること、それのみが唯一の存在証明となり得るのである。
あるいは僕自身も、掲出歌の号令の持つ響きに呼びかけられてしまった一人なのかもしれない。短歌の可能性を信じてみよう、そう思わせてくれる一首である。
海原にモゥビ・ディックを追ふやうに三十一音を追ふことはできぬか 田村 元
(初出:角川「短歌」2003.4)
<PR>